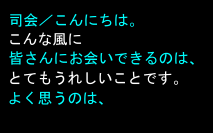 |
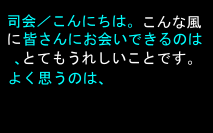 |
3.入力のしかた
C.入力のルール
iv.連係のコツ
★相棒の続きを打ち始めるのに、どこから打ち始めるか★
初めてパソコン要約筆記をする方が一番悩み、ベテランでも慣れない相手とコンビを組むときには、迷うところです。
これが正解というものはないのですが、判断材料をいくつか示しておきましょう。
1)一人が一行表示文字数以内を打つようにする
パソコン要約筆記ソフトの表示方式は、大別して2通りあります。
「i.表記のしかた」のところで、ご紹介したように、
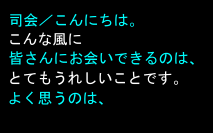 |
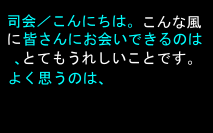 |
左の「それぞれが送信した文が、行を変えて表示される」形と、右の「二人が送信した文がくっついて表示される」形です。(IPtalk の場合、右の表示法で行を変えるには、エンターキーを空打ちします)
右の表示法をとると、文字が詰まって表示されるために、スクロールが少なくなり、たくさんの文字を出さないといけない場合に読みやすくなります。
逆に左の表示法では、スクロールは多くなりますが、意味の切れ目ごとに行が変わって表示されるため、文脈が読み取りやすくなります。
どちらの表示方式をとるかは、ケースバイケースで選択していただけばいいのですが、左の表示方式をとっている場合、一人が一度に打つ長さを1行表示文字以内にとどめれば、単語の途中で行が変わる「泣き別れ」が発生しないため、確実に読みやすくなります。
一人があまり長く打つと、送信までに時間がかかり、見ている人を長く待たせることになります。しかし、逆にあまり短い連係をすると、頻繁に相棒の動向を気にしなくてはならなくなりますので、集中力がもたなくなります。
一人が一度に、一行表示文字数(12〜3文字)以内を打つというのが基本と考えてよいでしょう。
2)相手が今打っているところより後の、きりのよいところから入る
「後」と書きましたが、どのくらい後なのかが問題です。
例を挙げて説明しましょう。
例文
「クリリンは、おそらく地球最強の戦士だ、」
Sさんが「クリリン」と打ち始めました。
今、「ン」を打ったところですから、Kさんは、「Sさんには『クリリンは、』まで打ってもらおう」と考えて、自分は「おそらく」から打ち始めました。
しかし、うまくいきませんでした。Kさんが打ち始めたことに、Sさんが気づいたときには、もう「クリリンは、おそら」まで打っていたからです。「おそらく」を二人が重複して打ってしまいました。
初心者にありがちな失敗なのですが、相手が今打っているところのほんの少し後から打ち始めてしまうと、2人の打つところが重なってしまいます。
Sさんは、Kさんが打ち始めたのに気づいてから、相手の打ち始めた言葉を読んで、それがどこなのかを判別し、自分がどこまで打つか決定します。決定までに、タイムラグが生じるわけです。その間にも、Sさん
自身は手を休めず、打ち続けていますから、Kさんの打っているところがどこか気づいたときには、もう二人の打っている箇所が重なってしまっているわけです。
重ならないようにするには、相手が今打っている文節の一つか二つ先の文節から、自分が打ち始めないといけません。
3)相棒の入力速度が速いときには、通常より後の位置から引き取って打ち始めるよう気をつける
先の例だと、Sさんが「クリリン」と打ったときに、Kさんが「地球最強の」から打ち始める。通常はこのくらいで大丈夫でしょう。
しかし、Kさんの入力速度が遅く、Sさんが速かった場合、Kさんが「ちきゅ」と打ち始めたときに、もうSさんが「クリリンは、おそらく」まで打ってしまっていることがあります。Kさんはまだ「ちきゅ」としか打ってませんから、Sさんには、Kさんが「地球最強の」と打とうとしていることが一目でわからず、その後も続けて打ってしまって、二人が「地球最強の」を打ってしまいました。
二人の入力速度に差がある場合に、こういう重なり方をすることは珍しくありません。
相棒が自分より打つのがかなり速いときには、通常より1文節か2文節、後から引き取って打つ(=相手に長く打たせる)ように心がけた方がいいでしょう。相手が速ければ速いほど、後から
打つことになります。
入力速度に差がある場合、速い人が長目に打ち、遅い人が短目に打った方が、スムーズに連係できます。
読みやすさという観点からすると、あまりいいことではないかも知れませんが、背に腹は代えられません。
4)自分の打った文を送信する前に、直前に送信された文をちらっと読んで、うまく繋がっているか確認する
連係がうまくいかず、前の文と一文節重なったり、逆に言葉が足りずにうまく繋がらないことがあります。そういう場合、重なっている頭の部分を消したり、うまく繋がるように言葉を補ってから、送信しましょう。
言葉を補うためは、自分の打っているところだけではなく、その前後の言葉も記憶にとどめておかないといけません。
5)二人の打っている文が重複している場合、どちらが消すか
重なって打っているのに気づいたとき、いきなり消したりせずに、まず手を止めて相手の動向を探ります。(あわてて二人が消してしまうと困るので (^-^;)
Sさんが、「クリリンは、おそらく」と打ち、Kさんが「おそらく地球最強の」まで打ったときに、双方が重なりに気づき、手を止めたとしましょう。この場合は、Kさんが文頭まで戻って、「おそらく」を消すより、Sさんが現在カーソルのある文末の「おそらく」を消す方が早いので、Sさんが消します。
しかし、Sさんが「クリリンは、おそらく地球最強」まで打っており、Kさんが「おそらく地球最強の」まで打ってたとしましょう。ここまで重なってしまっていると、Sさんが文末を1文字ずつ消していくより、KさんがESCキー等で全文を一発消去してしまった方が早いですし、
後から打ち始めたKさんの方が後の文をより多く記憶しているはずですので、Kさんが全文を消し、その後を打ち始めた方が効率がよく、聞き落としが少なくてすみます。
重複した場合、文頭に戻って消すのが早いか、文末を消せば早いかといえば、後者の方が早いので、先に打っている方が重複部分を消すのが原則なのですが、ほとんど重複してしまったときには、後で打ち始めた方が全文を消し
た方がいいでしょう。
後で打ち始めた人の方が、後の部分を覚えているため、続きを打ちやすいですし、消すのにかかる手間が、全文消去の方が少なくてすむからです。
相棒がほとんど重複しているのに気がついておらず、消して次を打ってもらいたい場合は、「消して」とか「いらない」と声をかけます。
なお、パソコン要約筆記ソフトでは、ESCキーに全文削除機能が割り当てられていて、なおかつESCで全文削除したときには、SHIFT+ESCなどで消した文を元に戻すような機能を備えているものがあります。そうしたソフトでは、BSキーやDELキーを使わずに、ESCで消せば、あわてて二人が重複した文を消してしまった場合でも、SHIFT+ESCで消した文を復活させることができます。
6)固有名詞、数字など覚えるのが難しい言葉から打ち始める
覚えにくい言葉を、長く覚えていて打つのは大変です。数字や覚えにくそうな言葉が出てきたら、そこから(あるいは、それを含む文節から)打ち始めてあげましょう。前に打っている人が打ちながら、難しい言葉を記憶せずにすみます。
7)相手が打ちにくい言葉から打ち始める
相棒がかな入力で英数字の入力が苦手だった場合、自分の方が打ちやすいようなら、その部分から打ち始めましょう。
自分が、長い単語を短縮登録や推測変換ですぐ出せるようになっていて、相棒がそうでない場合も同じです。
8)相手がタイピングや変換で手こずっている場合、そのすぐ後から打ち始める
タイピングミスを直しているとき、うまく変換できないで苦しんでいるときには、耳がお留守になります。相棒はすぐ後から打ち始めて、助けてあげましょう。逆に、自分が引っかかった
直後は、相棒の動向に注意しましょう。普通より前から打ち始めてくれているかも知れません。
但し、大幅な要約連係(それぞれが長い文を要約して打つ)をしているときは、この限りではありません。相棒を助けにいってしまうと、後の文が打てなくなります。
9)話者の変わり目から打ち始める
話者が変われば、行を変えて行頭から打ち始めないといけません。
ですから、当然打ち手が変わることになります。
ただ、「残りこの位なら、一人で最後まで打ち切ってしまえるだろう」と、相棒に長文を入れさせて、自分が次の話し手が登場するのを漫然と待っている・・というのは、感心しません。待っている時間があるなら、最後の部分を手伝ってあげれば、それだけ見ている人を待たせずにすみます。
「一人で打てるかどうか」という入力者側の事情ではなく、「できるだけリアルタイムに読みたい」という見ている側のニーズを優先させましょう。
10)一人が打つ長さについて
1)で一人が12〜3文字打つのが基本線であると書きました。
ただし、これはあくまでも話者の話すスピードが遅かったり、間が長かったりして、話者のスピードに追いつけている場合の話です。
話者の話す速度が速ければ、到底打ち切れず、読み手も読み切れなくなってしまいますから、「要約」が必要になってくるわけです。一人の分担量が長ければ長いほど、大幅な要約がしやすくなります。従って、話者の話す速度が速いときには、それぞれが長い範囲を受け持って連係します。長い範囲というと、いささか曖昧な表現なんですが、文の切れ目、複文構成の場合は単文の切れ目、話者の変わり目で、続きを引き取るのが通常でしょう。
一人の守備範囲を広げて要約入力しているときは、お互いの打ち始めを見誤ったり、見損なったりしやすくなります。相手が打った文を送信したら、どんな文を送ったのか
を確認し、自分の文ときちんと繋がっているか確認しましょう。
コンビの入力速度に差があるとき、「ちょっと長いけど、相棒に任せておけば、打ってくれるだろう」と考えて、ついつい文末までを任せてしまう。ありがちなんですが、
9)でも述べたように、カブらないようなタイミングで入れるときには、残りを打ってあげるようにして下さい。
11)聞き落とし対策その1…要約しながら聞く
話者の言葉を聞きながらどう要約するか考え、要約した文を記憶しておいて打ちます。長い文を記憶しておいて、打つ段階で要約し
ようとすると、要約文を考えているうちに、聞いたはずの言葉を忘れてしまうことがあります。
12)聞き落とし対策その2…打ち終わりに近づいたら、耳に神経を集中
変換に頭を使っているときには、耳がお留守になります。打ちながら、常時聞き続けることは不可能です。また、聞きながらうまく要約できなかったときには、打ちながら要約を考えることになります。そういうときは、耳は使えません。
しかし、自分の持ち分の終盤にかかっているときには、もう要約を考える必要はなくなりますし、ちょうど文の終末部分を打っているような場合には、定型的な文言を打つことになりますから、誤変換の心配も
あまりありません。打ち終わりにかかっているときには、脳に余裕があります。ですから、打ち終わりにかかったら、もう次に自分が打つべき言葉を聞くようにしましょう。早めに次の言葉を頭に入れておいて、手が空いたら
すぐそこから打ち始めるようにすれば、相棒の負担を軽くでき、全体として抜け落ちる部分が少なくなります。
自分の分担分を打ち終わってから、「さて、次に打つ言葉は・・・」と聞き取りを始めているようでは、遅いのです。
話に追いつけるかどうか危ういとき、余裕がないときには、耳を使うのは自分が打ち始めたところから、相棒が打ち始めた部分の直前まで。あとは、打ち終わりにかかったとき。これが最低限の聞き取り箇所です。
(本当は、自分の打つ部分の前後まで覚えていられるといいのですが)
苦しいときは、 「次を聞けるかどうか」が、勝負の分かれ目になります。聞くことができれば、要約でしのげますが、聞いていなければ丸っきりお手上げです。
★遅れっぱなしではなく、早く追いつく★
パソコン要約筆記では、聞いてから打ちますから、話者がしゃべってから字幕が出るまでの間に、タイムラグ(遅れ)が生じます。
しかし、長時間ずっと遅れっぱなしだと、頭が疲れてしまい、聞き間違いや聞き落としが出てきます。また、利用者に応答を求めるようなところは、できるだけタイムラグなしで出す必要があります。
幸い、話者は、ずっとしゃべりっぱなしではなく、文と文の間である程度間を置きます。文の途中で、言葉を止めることもあります。そこで、追いついておけば、入力者は頭を休めることができ、読み手もリアルタイムに情報が受け取れます。
パソコン要約筆記では、「遅れる」とはいっても、ずーっと遅れっぱなしなのではなく、「遅れては追いつき、遅れては追いつき」を繰り返しているのです。
「追いつく」ためには、文末をできるだけ速く打てるよう、一定のフレーズを集中的に練習したり、省入力候補として登録しておいたり、短縮登録したりしておきましょう。また、要約で文末を縮めても構いません。
「この文は打たない」という決断をすることで、追いついてもいいのですが、無闇にあちこち落とすわけにはいきません。どうしても落とせない箇所はあります。
速く打てるフレーズを増やし、文末を早く打てるようになると、追いつくのが楽になります。