3.入力のしかた
B.連係入力の実際
基本は前述したとおり、単純なんですが、実際にはそれほど簡単にはいきません。
パソコン要約筆記者であるSさんとKさんが入力の際にどんなことに注意を払っているのか、見ていきましょう。
司会者の挨拶が終わり、講演が始まりました。
講演者のBさんが「おれは、サイヤ人の王子として、これほど悔しい思いをしたことはなかった。下級戦士のカカロットはおろか、その息子、地球人との混血の悟天にまで後れをとるなんて。」としゃべっています。
これをKさんとSさんは、どのように連係して打っているのでしょう。
- 「Sの耳」「Kの耳」とある行は、SさんとKさんの耳に入っている声です。
色が濃い部分は、注意を集中して記憶しながら聞いている部分、色が薄い部分は、流して聞いているといいましょうか、「なんとなく聞いている」部分です。
いくら打ち終えたら忘れられるといっても、聞こえてきた言葉を全て覚えていることはできませんので、自分が打つ部分の前後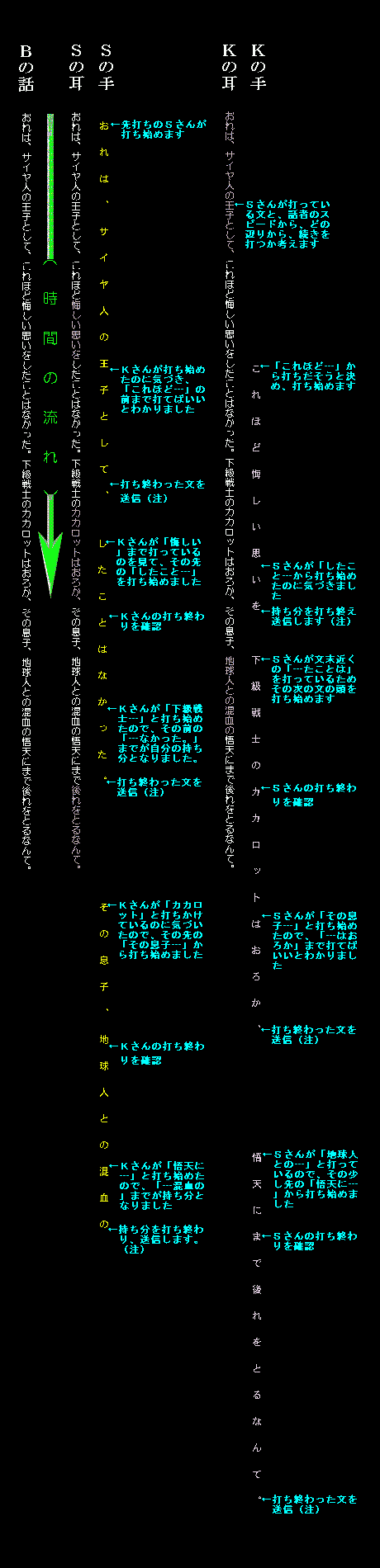 に集中して聞いている、覚えていることがわかります。
に集中して聞いている、覚えていることがわかります。
- 「Sの手」「Kの手」とあるのは、Sさん、Kさんがそれぞれ打っている文です。
Bさんのしゃべりや聞いている文に比べると、文字と文字の間がちょっと間延びしていますね。
SさんもKさんも、しゃべるのと同じ速さで打つことはできません。しゃべりに対して打つのが遅れるわけで、文字間の空白が、その遅れを意味しています。
さて、Sさんに注目してみましょう。
- 「おれは・・」と聞いた言葉をすぐに打ち出しました。
- 打ちながら、Bさんの話に耳を傾け、自分の打たなければいけない部分を覚えるとともに、モニタ欄に表示される相棒のKさんの入力を待ちます。
- Kさんが「これほど・・」から打ち始めました。
「これ・・」と聞いた瞬間打ち始めておらず、少し間をおいて打ち始めていますね。
Bさんの言葉を聞きながら、「Sさんにどこまで打たせようか?」とか、「この言葉は打つ価値があるか?」など、いろいろ考えてから、「ここから打とう」という判断を
していますので、打ち始めるまでに、多少の間ができます。
- さて、Kさんが打ち始めましたので、Sさんの持ち分が確定しました。
持ち分が確定したら、自分の残りの文をできるだけ速く打つようにがんばります。
打ちながら、耳に神経を集中して自分が次にどこから打ち始めたらよいか、考えます。
自分の分担部分が確定していますので、「残りを打つのに時間がかかりそうだ」と思ったら、「要約」をして打つ文を縮めてしまって構いません。
但し、ここでは「聞きながら、自分が次に打つところを考え、打ち始めを記憶する」ことに一番気を配らなければなりません。打つこと、要約することに頭を使っているようでは次に打
たなければならない言葉が耳に入ってこなくなります。
聞くことがおろそかになっては、何も打てなくなりますので、要約・文の整理は、リアルタイムに行ないましょう。聞くと同時に打つ文を作って、記憶しておく感じです。
- 自分の分担分「・・として、」まで打ち終わりました。
ここで、一つ気をつけなければいけないことがあります。
表の中でも(注)としてありますね。
自分の打った文をエンターキーで送信する前に、送信済みの文が表示されているウインドウをちらっと見て、そのまま送信しても大丈夫か、うまく文が繋がるかを確認してください。
もし、相棒のKさんが「これほど・・」から打ち始めたのに、途中で消して他のところから打ち始めていたら、自分の文の頭やおしりの部分を削ったり付け足したりして修正しなければなりません。
また、発言者が変わっていて、行を変えて出したり、頭に発言者名をつけて 出さなければならない場合もあります。
打ち終えたらすぐ送信するのではなく、つながりを確認してから、送信する癖をつけましょう。
- 自分の打った文を送信したら、相棒が今打っている部分と、自分が聞き溜めしている文を比べ、次にどこから打ち始めるかを決めます。
ここで気をつけたいのは、相棒が今打っている部分のすぐ後ろから打ち始めると、自分が打ち始めた部分を相棒も打ってしまうことがあることです。
相棒が今打っている箇所の少し後から打ち始めるようにしましょう。
ここまでが1セットの作業で、あとは同じことの繰り返しです。結構複雑な作業をしていますね。
聞いて覚える・要約する・打つという作業を同時にこなさなければならないので「次に何をやって・・」なんて考えていたら、とてもできません。しかし、連係練習を繰り返し、一連の作業を体に覚えさせると、不思議とできるようになるものです。


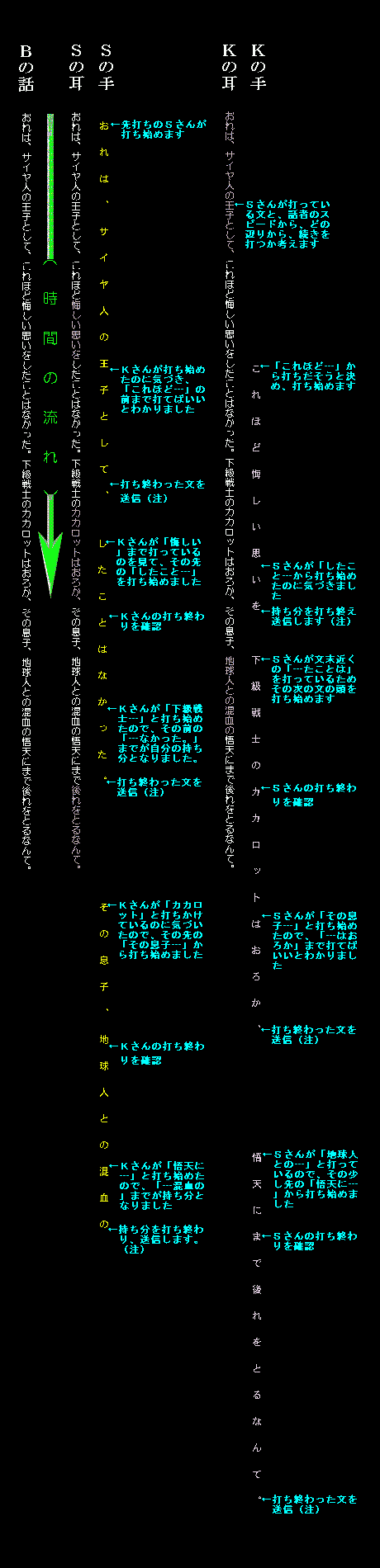 に集中して聞いている、覚えていることがわかります。
に集中して聞いている、覚えていることがわかります。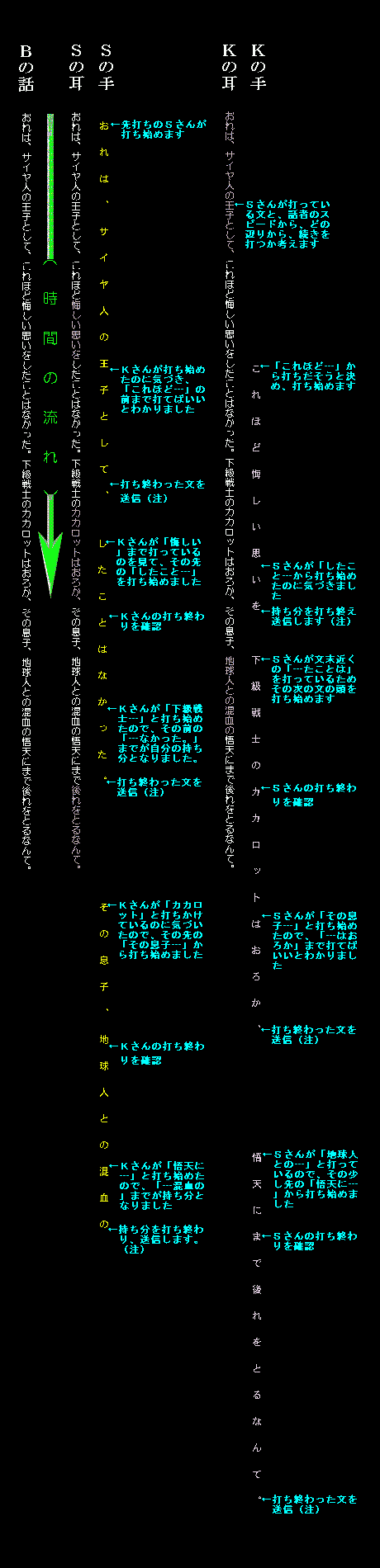 に集中して聞いている、覚えていることがわかります。
に集中して聞いている、覚えていることがわかります。